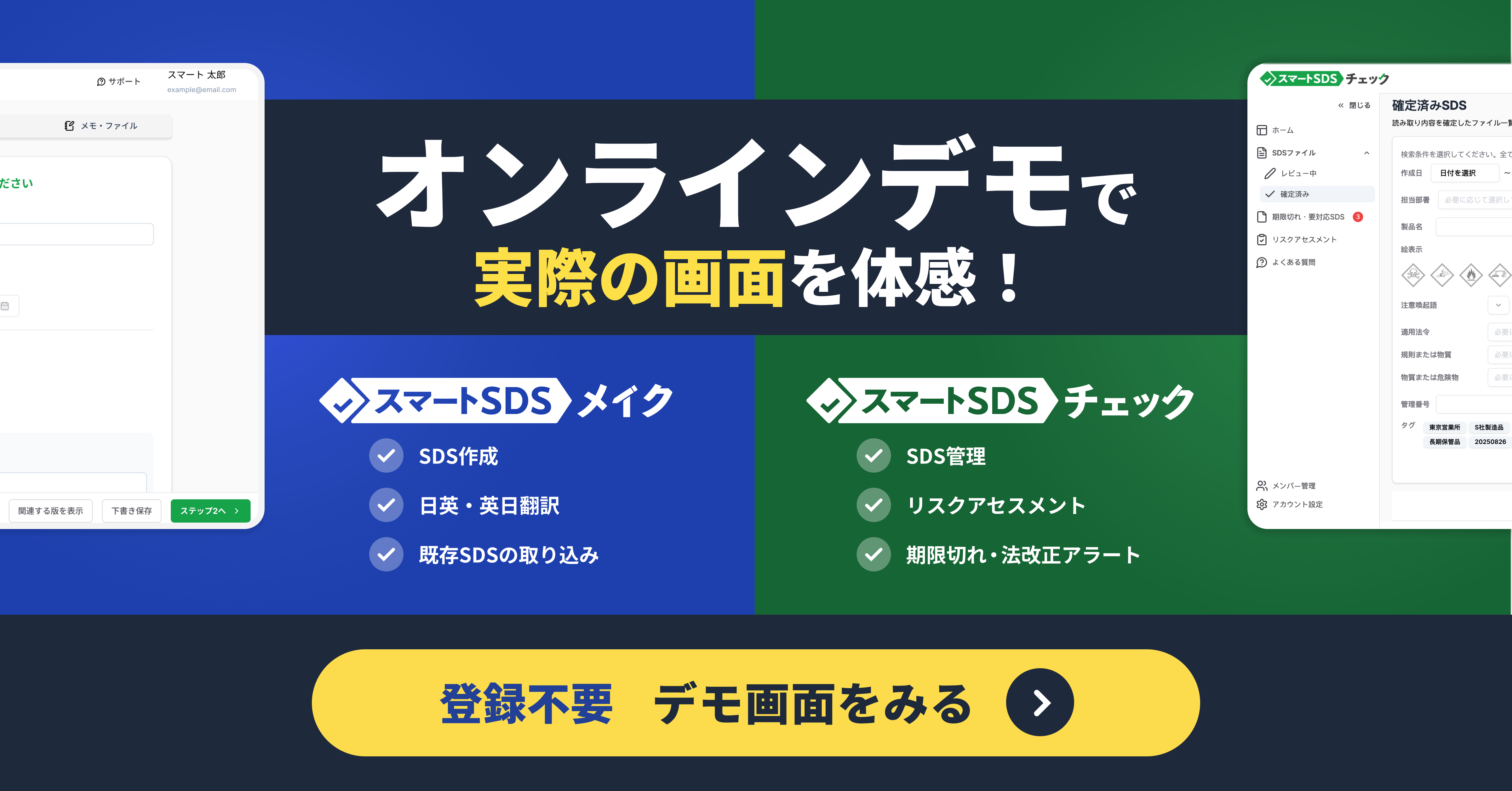SDSの保管義務について:保管場所や期間、効率的な保管方法についても解説
更新:2025.07.30スマートSDSメディア編集部
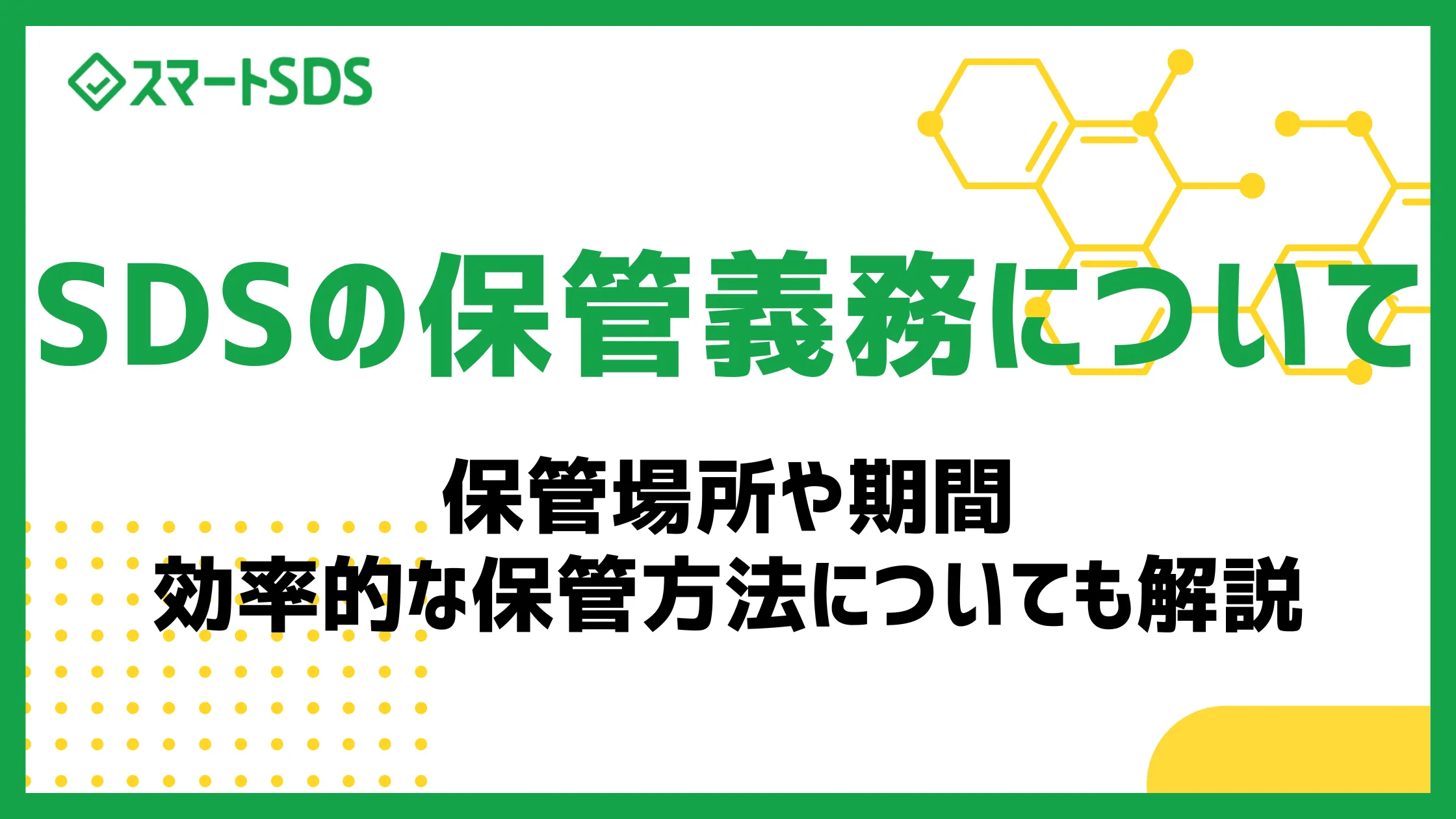
SDSの保管はどのように行っていますか?
SDSは定期的な更新や周知の必要性があるため、適切に保管しておくことが非常に重要です。
本記事では最新の労働安全衛生法などの諸法律に基づき、SDSの保管義務や、保管すべき期間・場所、効率的な保管方法について解説します。
SDSとは
SDSは化学品を他の事業者に譲渡または提供する際に、その物質の危険性や取り扱い方法などを伝達するために作成されるものです。
SDSの交付はある特定の化学物質を一定上含む製品に対しては交付が義務付けられており、その具体的な物質名や基準値などは労働安全衛生法や化学物質把握管理促進法(化管法)などの法令によって定められています。
2025年4月現在ではSDS交付義務対象物質として約1600の化学物質が登録されており、今後も法改正によりその数は拡大していくことが予定されています。最新の報告では、2026年までに約2300の物質が登録さ�れる予定であり、今までSDSを作成してこなかった事業者にとっても対応が急務となっています。
なお、SDSに関するより具体的な情報に関しては別記事「SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!」をご覧ください。
SDS保管義務
SDS交付義務対象物質は、リスクアセスメント実施義務対象物でもあります。したがって、取引先からSDSを受け取った場合、SDSにもとづきリスクアセスメントを実施しなければなりません。リスクアセスメントは一度実施すればいいというものではありませんし、リスクアセスメント以外にも様々な法令義務があります。
SDSの保管義務に関して明確に示している文書は現状ありませんが、SDSに対するさまざまな義務を考慮すると保管は前提になっていると考えて良いでしょう。
なお、リスクアセスメントに関しては別記事「化学物質のリスクアセスメントとは? 対象物質ややり方について簡単に解説」をご覧ください。
SDSの保管場�所
それでは、SDSはどこに保管しておくべきでしょうか。
結論としては、SDSはどこに保管しておいても大丈夫です。紙媒体でも電子媒体でも構いません。
作業場への備え付けについて
SDSの保管場所に関するよくある質問として、「SDSを作業場に備え付けるべきか」というものがあります。
こちらに関しては、法令上は「労働者に対するSDSの周知ができていれば備え付ける必要はない」ということになります。
ただし、SDSにはその内容を労働者に周知する義務があります。労働者が内容を常時確認できるようにしておく必要があるため、実態としてはSDSを作業場に備え付けておくことが望ましいです。
参考:SDSの周知
SDSには、その内容の周知義務が労働安全衛生法で定められており、以下のいずれかの方法で化学物質を扱う労働者が内容を常時確認できるようにしなければなりません。
- 作業場に常時掲示するか備え付ける
- 書面を労働者に交付する
- 電子媒体で記録し、作業場に常時確認可能な機器(パソコンなど)を設置
SDSを保管すべき期間
SDSの保管期間については、無期限であると考えておくべきでしょう。
SDSの定期更新義務や法改正対応、周知義務に関しては期間が定められていないためです。
したがって自社が交付しているSDSに関しては無期限で、交付を受けたSDSに関してはその化学物質を使用している限り保管しておくべきでしょう。
効率的なSDSの保管方法
SDSは更新義務などに効率よく対応するため、適切な保管方法を取ることが大切です。
しかし、
・リスクアセスメントをする際に必要なSDSがすぐに検索できない
・法改正等で更新が必要になるSDSがどれかわからない
などといった悩みがある企業も多いのではないでしょうか?
そこでおすすめしたいのがSDS受取・管理クラウド「スマートSDSチェック」です。

スマートSDSチェックでは、既存のSDSをPDFから読み取り、統一的なフォーマットで一元管理することが可能です。
また、法改正等で更新がSDSが発生した場合には、システムが自動で検知しアラートを出します。
さらに、標準的なリスクアセスメントツール「CREATE_SIMPLE」と連携し、リスクアセスメントの実施を効率化します。
期間限定で無料トライアルプランもご用意しております。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。